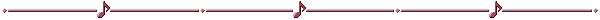CDの入手方法のお問い合わせは、メールでお願いします。
1stアルバム収録曲解説
「コンフント・アンデス~アンデスの風と共に」
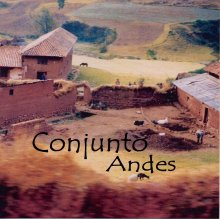
<製造番号>CONJ-03041
<JASRAC登録>R-0321057
| 1. | エル・シクーリ El Sicuri | 4'00'' |
| 馬渡:Q,Z 萩原:Cg 井神:G 内藤:Guilo 永塩:B 宮下:Vo | ||
|
ケーナの総帥アントニオ・パントーハの作品です。シクーリとはシーク(サンポーニャ=葦を並べた笛)を吹く人という意味です。
私(馬渡)が、フォルクローレという音楽に足を踏み入れた曲です。 ビエントス(風)の音を感じていただけたらと思っています。 | ||
| 2. | イミリータイ Imillitay | 3'11'' |
| 馬渡:Z,Vo 萩原:Cg 井神:G 直原:Z,B,Vo 内藤:Z,Vo 永塩:B 宮下:G,Vo | ||
|
ロス・カルカスの名曲。力強いティンクのリズムですが、詞は切ない失恋の歌です。
イミリータイ(Imillitay)とは、フォルクローレによく出てくるパロミータ(Palomita)、ネグリータ(Negrita)と同じ語義で「俺のカノジョ(英語のベイビーbaby )」という感じのようです。 「"愛しているわ"と君は言った。でもそれは嘘だった。いつも僕を弄んで。けれど今も君を愛している。君を忘れようと暮らしているが、忘れられない。 君の想い出は、棘のように僕の心を傷つける。」 いつの世もどこの国でも、傷ついた男の心は立直りが遅いようです。 | ||
| 3. | コンドルは飛んでいく El Condor Pasa |
4'10'' |
| 馬渡:Q,Z 萩原:Cg 井神:G 永塩:B 宮下:Vo,Chf | ||
| 皆さんご存知のフォルクローレの名曲、El Condor Pasa(コンドルは飛んで行く)。 ペルーの作曲家ダニエル・アロミーア・ロブ レスが1913年に発表した、アンデスの音楽を代表する曲ですね。 サイモンとガーファンクルで大ヒットしたことを知っているのは、40歳以上の人達だけになってしまったのかな。以前は小学校の教科書に載っていたのですが。 | ||
| 4. | エル・アンティガル El Antigal | 3'49'' |
| 馬渡:Q 萩原:Cg 井神:G 直原:B 宮下:G | ||
|
アルゼンチンの(ブラジルのとは違って、ゆったりと趣のある)サンバ(ZAMBA)というリズムのフォルクローレ。 アンティガル(古きもの)とはアルゼンチンのサルタ州の言葉で先住民族の遺跡を指します。 その神秘を描こうと詩人ペトロチェリ、 歌手ダニエル・トロ、ギタリスト、リト・ニエバスの3人が合作した曲です。 ロス・ライカスの名演に魅せられたグルーポ・カンタティの演奏 (チャランゴ入りボリビア風アレンジ)を参考にしました。 音を拾うこと、チャランゴの運指、ケーナの音域の広いメロディ、難しい曲でしたが、なぜかこのCDの中で最初にOKテイクが出た曲でした。 | ||
| 5. | クティムイ Kutimuy | 4'41'' |
| 馬渡:Q,Z,Chf 萩原:Cg 井神:G 直原:B,Vo 宮下:G,Vo | ||
|
ロス・カルカス初期のヒットナンバーでゴンサロ・エルモッサとウリーセス・エルモッサの作品です。
美しいメロディが印象的な曲でリズムはワイニョ。クティムイとは「帰ってきて」を意味するケチュア語(インカ帝国の国語)です。
去っていった恋人を想って悲しく生きている若者の歌でボリビア版の演歌でしょうか。歌詞はスペイン語です。
女性ボーカルでシンプルに仕上げたグルーポ・カンタティのアレンジを参考にしています。
「恋人よ、帰ってきておくれ。いつまでも待っている。君のいない人生なんて悲しい。とても悲しくて、君のことばかり考えている。お願いだ、帰ってきておくれ。 君がいないのは耐えられない。君は私の生きがいだった。今は絶望だけ。明日も悲しくなる。君がそばにいないのなら。」 | ||
| 6. | モージェの木 Surapata Mollecito | 2'45'' |
| 直原:Q 永塩:Q 馬渡:Q,B 萩原:Cg 井神:G 宮下:G | ||
| ボリビアのグループ、カナタのC.サラマンカの作品です。 カナタの曲はレコード盤のみなのでご存知の方は古くからのフォルクローレファンではないでしょうか。 リズムは6/8拍子のバイレシート、素朴な味わいを持った曲で 後半はケーナ三重奏になっています。 西洋の厳格な楽器と違いケーナは音程も音質も おおらかですから、笛により違いが大きく、また吹き手によっても音色が異なります。 そのアンサンブルをおおらかにお楽しみください。 アンデス原産のモージェの木は、繊細な姿だけれど土質を選ばず少ない水でも育つ 強くたくましい木だそうです。 | ||
| 7. | シクーリス Sicuris | 3'18'' |
| 現地インディオの言葉アイマラ語でSicu(シーク)という葦の管を並べた楽器の合奏です。 「ドミソ・・」と連ねた管と「レファ#ラ・・」と連ねた管をそれぞれ別の演奏者が交互に音を出す、コンテスタード(contestado)という本来行われた奏法で演奏しています。 一方を「導くもの」、もう一方を「導かれるもの」とも言うようで、コンテスタ(contesta)の意のとおり、両者の”応答・会話”の様子を感じながら聴いて下さい。 | ||
| 8. | クラワーラ~クシクシ Curawara~Kusi Kusi | 3'49' |
| 永塩、内藤、直原、萩原、宮下:Tarka 井神:G 馬渡:Wancara | ||
| タルカという木彫りの笛と打楽器のみで演奏されるタルケアーダの曲です。 調子が外れたような音色ですが、音程は合っています。同じ作者が同じ時に作ったものでないと合わないようです。 同じフォルクローレでもこれらの音楽はアウトクトナと呼ばれ、スペイン人が新大陸に入ってギターやチャランゴ等の弦楽器が持ち込まれてからの音楽、クリオージョと区別されます。 朴訥な音色と力強さが魅力のタルケアーダは、アンデスの主食ジャガイモの収穫祭に演奏され、人々は空と大地の恵みに感謝を捧げるのです。 | ||
| 9. | プルルーナス Phuru Runas | 3'35'' |
| カルカスのインストルメンタルの名曲です。リズムはワイニョ、ケーナのハーモニーとトヨスの掛け合い、とフォルクローレの魅力を満載した聴き所の多い曲です。 | ||
| 10. | チャランギート Charanguito | 3'12'' |
| 萩原:Cg | ||
| ボリビア、コチャバンバを代表するチャランゴの名手、アレハンドロ・カマラの独演に挑戦してみました。 と言えば聞こえは良いのですが、曲の途中のリズムが変わる(ティンク⇒ワイニョ)箇所で、OKテイクを継ぎはぎ出来ると踏んで決めた曲でもあります・・(結果はメンバーのみぞ知る)。 ちなみにチャランギートとはチャランゴ奏者の意味です。普段はケーナやサンポーニャの伴奏にまわるチャランゴですが、このようにソロ楽器としての可能性も充分秘められているのです。 | ||
| 11. | ベニの浜辺で En las Playas del Beni | 3'10'' |
| 萩原:Cg、宮下:G | ||
| Lola Sierra de MendezとJose Aquirre Achaによる、幾多の演奏家達が取り上げている美しい旋律を持つ名曲ですが、こちらは先の「チャランギート」同様、 名手アレハンドロ・カマラによるヴァージョンです。 ちなみにベニとは、「紅」ではなくて、ボリビアのベニ州の事です。一般にフォルクローレというとアンデス山脈のイメージが強く、何処までも青い空にコンドルが飛んでいるという感じですが、 ベニはボリビア東部に位置する、ワニ等が生息する湿地帯。 この曲も熱いロマンスを歌ったものだとか・・・ちなみに演奏が何やら震えているのは、熱に浮かされている訳ではなくて単にひどく緊張していたからです。 | ||
| 12. | リャキ・ルナ Llaqui Runa | 5'33'' |
| 馬渡:Q,Z 永塩:Q,Chf 萩原:Cg 宮下:G 直原:B | ||
| ボリビアの伝承曲。リャキ・ルナとはケチュア語(インカ帝国の国語)で「悲しい人」の意。 ギターとチャランゴによる前奏と間奏を除けば同じメロディの繰り返しですが、音の低いケナーチョという長いケーナを使用したり、 楽器の組合せやハーモニー・音量の変化によって次第に盛り上がってエンディングを迎える構成となっています。 レコーディングでOKが出るまで最もこだわってしまったのは、一回目のメロディ中で聞こえる「雨の音」の楽器Palo de Lluvia(西:雨の滴~英名レインスティック)でした。 5分を超える長い曲で、初めから終わりまで弾きっぱなしのギターは、寒い日だったのでよけいに指がしんどかったようです。 | ||
| 13. | コーヒー・ルンバ Moliendo Cafe | 2'50'' |
| 馬渡:Q,Z,B 永塩: 萩原:Cg 宮下:Vo,G 直原:Chf | ||
| ベネズエラのアルパ(ハープを小さくしたサイズの南米の楽器。)奏者、ウーゴ・ブランコの演奏で1961年に世界的にヒットしました。 ブランコによるとオルキディアというリズムですが、日本では、西田佐知子、荻野目洋子、井上陽水がいずれも原曲と関係のない能天気(?)な歌詞で ルンバ(共通点が多くポピュラーなリズム)としてカバーしました。 原題「モリエンド カフェ」とは、コーヒー園の奴隷が「コーヒーを挽きながら」哀しい、尽きせぬ想いを歌っている詞です。 原題を知る私のスペイン語仲間は残念がりますが、日本でのポピュラリティーを優先して、このむちゃくちゃな歌詞版によりアップテンポで演奏してみました。 | ||
| 14. | 花祭り El Humahuaquenho | 2'51'' |
| 馬渡:Q,Z,Vo 永塩:Q,Vo 萩原:Cg 井神:G 内藤:B,Vo 宮下:Vo,Chf 直原:Vo | ||
| アルゼンチンのエドモンド・サルディバルが、インカの楽しいカルナバリートの曲を採譜して1943年に"エル・ウマウァ ケーニョ"(ウマウァカの人)として発表しています。 これが1953年に"花祭り"としてフランス語の歌詞がつき、シャンソンとなってパリでヒットしてから世界中で知られるようになりました。 アルゼンチンの最北端、ウマウァカでのカルナバルの雰囲気を味わっていただき、コンフント・アンデスの楽しい歌声も聴いていただければ嬉しく思います。 カルナバルとは、2月末に南米ではどこでも催されるお祭りのことです。 | ||
| 15. | ラ・クーナ La Cuna | 3'17'' |
| 馬渡:Z | ||
| サンポーニャの独奏です。少しゆったりとした演奏をしてみたいと思って作ってみました(馬渡の作曲です)。 実は曲のタイトルを何にし ようかと色々考えていたのですが、なかなかいい案が出てきませんでした。 何十回か録音してみて、さてどの録音を採用しようかなとメンバーと共に聴いていたのですが、私も含めて皆ウトウトと眠くなってしまいました。 何か眠気を誘ってしまう様な曲だなということから"ラ・クーナ"(ゆりかご)という名に落ち着きました。 聴いていただいて、安心して眠りについて頂いたら嬉しく思います。 | ||
2ndアルバム収録曲解説
「コンフント・アンデスⅡ~アンデスの大地に捧ぐ~」
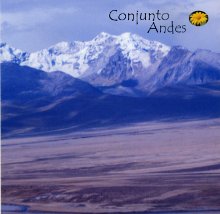
<製造番号>CONJ-10121
<JASRAC登録>R-1001053
| 1. | レーニョ・ベルデ Lenho Verde | 3'02'' |
| ご存じ、エルネスト・カブールの作品です。その当時、ジョニー・ベルナールのサンポーニャの音に聴き惚れていました。 8分の6拍子のチャランゴと、4分の3拍子のギターの伴奏に、ロング・ トーンの多いサンポーニャが乗る、緊張感に溢れる曲です。 | ||
| 2. | 湖の町 Ciudad del Lago | 3'16'' |
| この曲を初めて耳にしたのは、1982年に来日した Los Urosというセミプロのグループの演奏です。初めて生でフォルクローレの演奏を耳にして感動した頃を想いだします。 ペルーとボリビアの国境にある世界で最も標高の高い湖、チチカカ湖畔にある町(プーノのことでしょう) のことを唄った曲で、マリネーラの軽快なリズムに、さわやかなケーナの音色が湖の雰囲気を醸し出しています。 | ||
| 3. | 花祭り El Humauaquenho |
4'22'' |
| この2ndアルバムの花祭りは、イギリスのグループ、インカンテーションのバージョンを基にしました。 1stアルバムに比べるとゆったり感があり、聴きごたえがある作品に仕上がったのではと思っています。 | ||
| 4. | ロコティート Rocotito | 3'34'' |
| ウニャ・ラモスのアルバム、“土の人形”の中の一曲です。 曲名のロコティート(Rocote)とはアメリカ(中南米ですよ)でトウガラシの一種らしいのですが、この曲がどういう意図で作られたかは、私には分かりません。 原曲のウニャ・ラモスの力強い吹き方に比べて、このアルバムでは素直なビエントスという感じにまとめています。 ウニャ・ラモスがこのアルバムを聴いたらどう思うのでしょうね。 | ||
| 5. | インディオの哀歌 Elegia del Indio | 2'33'' |
| アンデスの笛<Ⅰ>ロス・カルチャキスのレコードの1曲目です。大学生の時、このアルバムを電通に勤めていた知り合いから借りてテープに録音しました。 フォルクローレのレコードはまだ広島にほとんどなく、このテープを毎日何回も何回も聴き込んだものです。 素朴で哀愁漂う静かなスローテンポの曲です。 | ||
| 6. | キルキンチョの夢 Suenho de Quirquincho | 3'25'' |
| エルネスト・カブールの曲で、もとはギターの伴奏が付いていますが、今回はチャランゴの独奏として録音しました。 「キルキンチョ」とはケチュア語でアルマジロの事です。 アルマジロは大変よく眠る動物だそうですが、楽器と化してしまった後はどんな夢を見るのでしょうか・・。 と、言いつつ、録音に使ったのは木彫りのチャランゴですが。 | ||
| 7. | 私の不運よ Mi Desventura | 4'07'' |
| ダイナミックながら何処か悲しげなサンポーニャのメロディーが映える曲です。 リズムはクェッカと言い(詳しい解説は玄人筋のHPに譲りますが)、形式上同じメロディーが何度か出てきますが、この曲は前奏・間奏ありと聴きどころも多くなっています。 | ||
| 8. | グアキの娘~モレーナ・コージャ Guaquenita~Morena-kolla | 3'05' |
| 1stCDに続きチャランゴの巨匠アレハンドロ・カマラの曲に挑戦しました。 モレナーダのリズムに乗って2つのメロディーが奏でられます。 が、原曲そのまま演奏するのは何とも畏れ多く、あちこち手を加えた挙句に、収められたヴァージョンになりました。 やや踏み外し気味のところもありますが、まあ、ご愛嬌ということでお許し頂ければと思います。 | ||
| 9. | 太陽の乙女たち Virgenes del Sol | 4'32'' |
| インカの古いメロディに基づいて、ママクーナたちに捧ぐべく、ブラボ・デ・ルエダによって作られた曲です。 ママクーナというのは永遠の処女を守りながら、神殿で太陽神に奉仕しなければならなかった乙女たちのことです。 マチュピチュで発見されたミイラのほとんどが若い女性で、自らの手で生命を絶ったものと推定されるものがかなりあったようです。 ペルーの代表的な曲の一つです。ケーナの二重奏をお聴き下さい。 | ||
| 10. | ビスペラス・デ・カルナバル Visperas de Carnaval | 2'50'' |
|
タルケアーダの曲です。 Los Kollanas というグループの素朴な演奏から取ってみました。
最後の部分にフォルクローレでは使われない打楽器を用いてみましたが、これが実にマッチしていると思ったので入れました。
10数年前に社員旅行で韓国に行ったときに買った打楽器で、“パンウル”と名前です。
右は私たちが使ったパンウルです。 | ||
| 11. | 素焼きの瓶 Vasija de Barro | 3'28'' |
| この曲は私たちが演奏しているぺルー、ボリビア、アルゼンチンではなくエクアドルの曲です。 前半は男性の力強い(?)ハーモニー、後半は素朴なケーナの二重奏を聴いてください。 | ||
| 12. | パンディニータ Pandinita | 2'15'' |
| Conjunto Andes の旧メンバーからこの曲が聴きたいとの要望があり、それではと入れてみました。 パンディニータとは“パンドの娘”という意味です。 パンドはボリビア最北部の町でラパス(標高3600m)とは違い、海抜280mの熱帯性気候の町です。 テンポのいい曲で、情熱的に歌い上げるボーカルが聴きどころです。 このアルバムの中では一番短い曲になりました。 | ||
| 13. | モレナーダ Morenada | 2'38'' |
| 古くからのフォルクローレファンならKANATAの名前をご存知かと思います。 その中の一曲です。このアルバムの中で最初にOKが出ました。 | ||
| 14. | コンドルは飛んで行く El Condor Pasa | 3'30'' |
ご存じ、ペルーの名曲です。ただしケーナは一切使わず、すべてサンポーニャで吹いています。
トヨ(サンポーニャの中で一番長いサンポーニャのボリビアでの呼び名です。
 写真の上がトヨ、下がマルタ(約30cm)です。)が出てきたり、サンポーニャでのハーモニーがあったり、サンポーニャのコンテスタード(サンポーニャの掛け合い)があったりします。
いろいろなサンポーニャの音が楽しめるのではと思っています。
写真の上がトヨ、下がマルタ(約30cm)です。)が出てきたり、サンポーニャでのハーモニーがあったり、サンポーニャのコンテスタード(サンポーニャの掛け合い)があったりします。
いろいろなサンポーニャの音が楽しめるのではと思っています。 | ||
| 15. | アンタラ Antara | 2'58'' |
| アンタラとはケチュア語でサンポーニャのことです。 原曲はペルーのペドロ・チャルコが吹くひなびた味わい深いケーナのヤラビです。 私はこの曲を以前アンデスの山の中にいた時のイメージを持って吹いてみました。 | ||
| 16. | アイマラ族のお祭り Fiesta Aymara | 4'22'' |
| コンフント・アンデスが以前から演奏している曲です。 確かタワンテインスージュというグループの演奏を基にしているのですが、今となってはそのレコードも、テープも、楽譜もありません。 どこに行ったのでしょうね。 この曲は、静かなイントロから、徐々に盛り上がり、いつのまにか激しいクライマックスへ。とても同じメロディーの繰り返しとは思えないドラマチックな展開の曲です。 タルカやモセーニョなどの珍しいアウトクトナ楽器の音色が聴けるのも魅力です。 このタイトル(アイマラ族のお祭り)の曲は、他にもいろいろあるようです。 | ||
| 17. | ポコ・ア・ポコ~アモロサ・パロミータ Poco a Poco~Amorosa Palomita | 4'09'' |
| マウロ・ヌニェスのポコ・ア・ポコは以前から演奏していましたが、今回CDに収録するにあたって、ハチャ・マジュクが演奏しているアモロサ・パロミータのカポ-ラルヴァージョンと合体させました。 楽器の多さ・構成のアレンジ・実際の録音作業など我々の手に余る部分もあり(おまけに途中でHDDレコーダーがクラッシュしてデータ救出が危ぶまれる事態に陥ったりと)、 今回の2ndCD中の最大の難曲・難局だったと思いますが、こうして無事収録出来たのは感無量です。 | ||
|
<お詫び> ごめんなさい。2ndCDにはミスプリントがあります。 CD帯のタイトル面 (誤)フィルクローレ → (正)フォルクローレ その他、CDジャケット中表紙の曲目原題に2点ほどミスがありました。このページに書いてある原題が正しい綴りです。 | ||